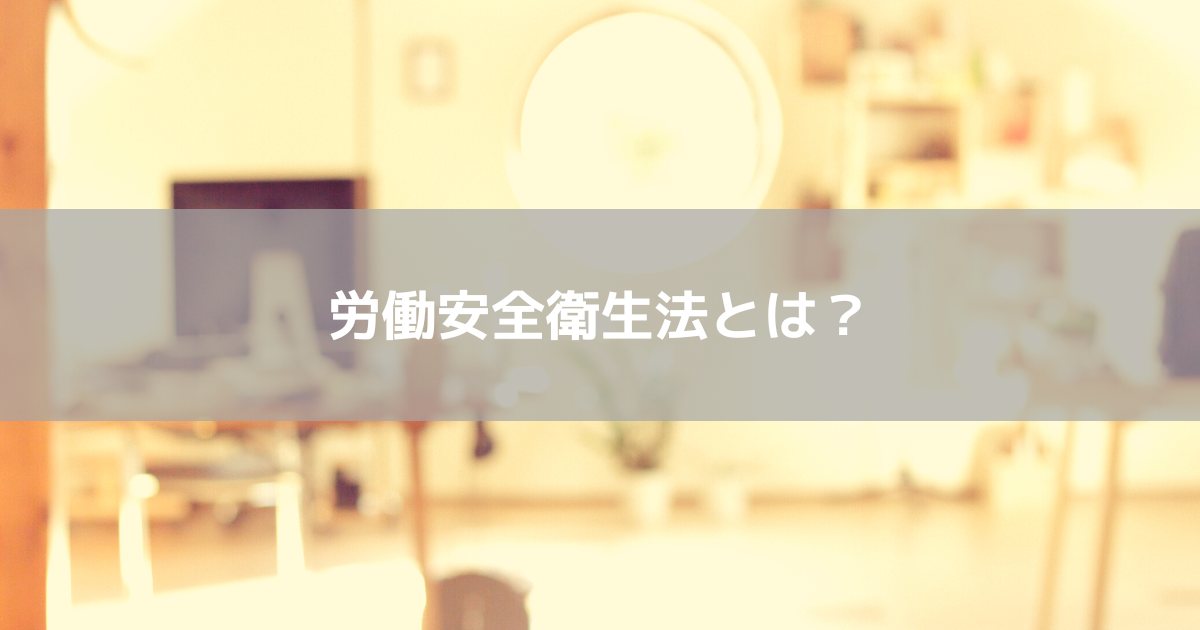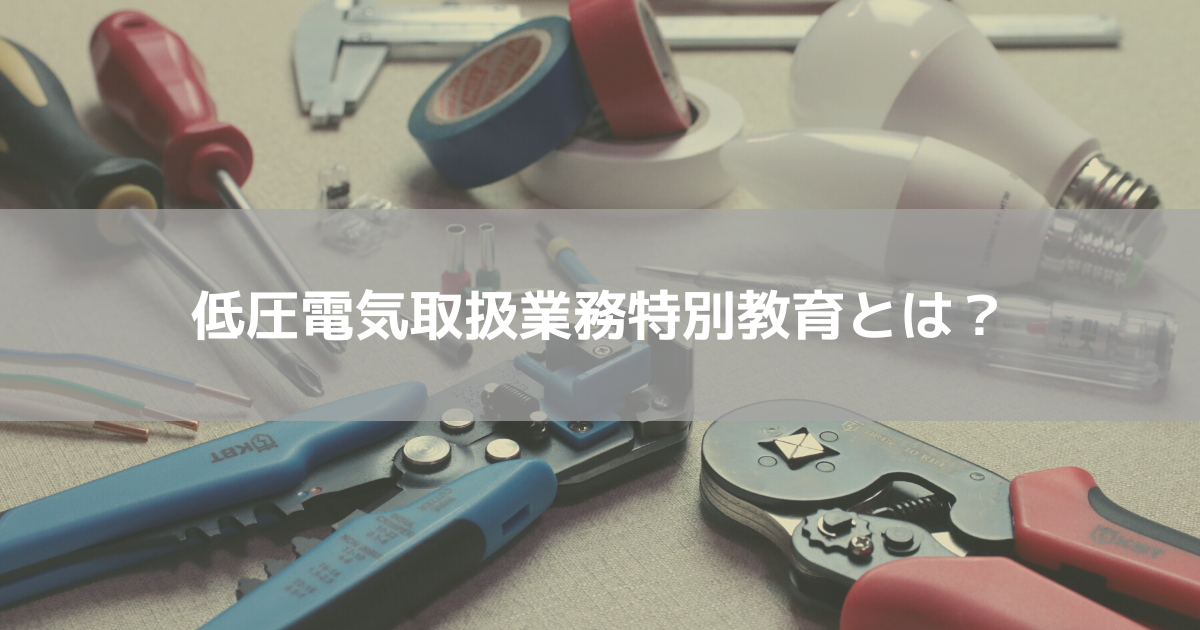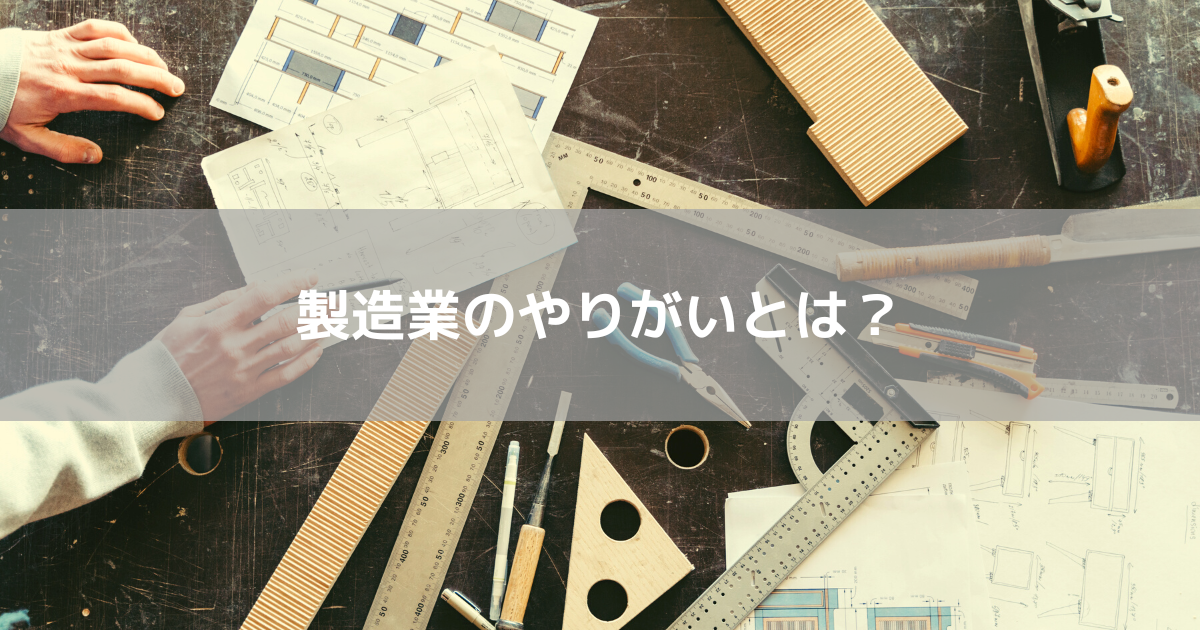製造業の生産計画をエクセルで管理するメリットは?デメリットと合わせて解説
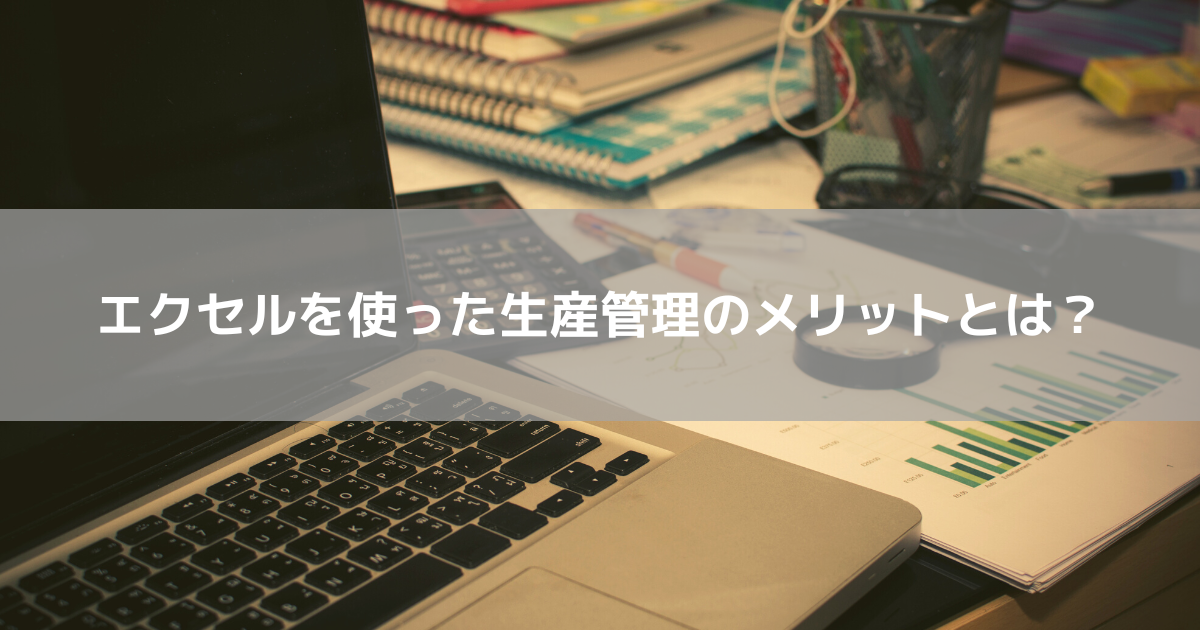
製造業の生産計画には人員配置や品質管理など様々な項目があります。そのため、一目でわかるエクセルを活用して効率化を図る方もいるはずです。
とはいえ、そのような管理は本当に生産性が高いのでしょうか。そこで今回は製造業におけるエクセルを使った生産管理のメリットとデメリットを中心に解説していきます。
製造業における生産管理、生産計画とは
製造業における生産管理とは受発注・在庫・品質管理などの総称を言い、その中に生産計画があります。製造業は依頼主に対し、決められた納期までに品質の高い成果物を納品していきます。そのため、納品までにおける工程を緻密に管理していく必要があるのです。
管理が徹底していれば各工程の見える化が実現し「どの工程で生産性が下がっているのか?」「どこのプロセスを改善すればいいのか?」などの分析が可能になります。
生産計画を立てる重要性
生産計画は業務効率を図る上で欠かせないフェーズです。「製品をどれくらいつくるのか?」「いつまでに完成させるのか?」などをとりまとめた計画になります。
言葉に計画とついている事実からも、計画無くして良い製品はつくれません。人も人生計画を立てて生きていくように、製品にも道しるべを示していく必要があるのです。
実際、右肩上がりに売上を伸ばしている製造企業は生産計画が綿密に立てられています。
生産計画と製造計画の違い
製造業における生産計画とは、生産する製品・時期・数量を決定する計画を意味しています。一方で、製造計画とは、製造現場における進捗・工程を決める計画のことを指します。
つまり、生産計画とは広範囲の生産工程を対象としており、製造計画は生産計画の一部の中の製造におけるプロセスを立案するということになります。
基準生産日程計画(MPS)とは
基準生産日程計画(MPS:Master Production Schedule)とは、受注の状況や在庫量を踏まえて、その製品といつまでに、どのくらい生産するか決める計画のことです。
基準生産日程計画は、生産計画の起点となっており、受注情報と製造計画を綱月ための大切な情報となります。
PRM(資材所要量計画)とAPS(生産スケジューラー)の違い
MRP(資材所要量計画)とは「Material Requirements Planning」の略称で、在庫管理を円滑にするために、生産に必要な資材の量や時期を決める計画のことです。
APS(生産スケジューラ)とは「Advanced Planning and Scheduling」の略称で、生産量に対して必要な資材を割り当てるための情報システムです。
なぜAPSが必要かというと、MRPのみでは生産不可の考慮をせず、資源が生産能力を持つことを前提として計画を立てているため、実現不可能な計画を立ててしまう恐れがあります。そのため、APSを使用して、資材の生産能力を踏まえて正確に、実現可能なスケジュールを立てる必要があるのです。
生産計画は期間別に計画することが重要
生産計画は、需要予測と原料調達計画、製造計画からなっています。
現実に即した計画の中で拡大成長をするためには、「大日程計画」「中日程計画」「小日程計画」と期間ごとに区切った生産計画を立てることが必須になってきます。この計画は期間別生産計画とも呼ばれます。
製造業で使える!生産管理表の作り方
Excelを使用した製造業の生産計画表の作り方について解説します。
①基準年月を設定する
まず初めに、基準年月を設定します。生産計画表の作成では、3つの異なる期間に合わせた計画が必要となります。
大日程計画:3〜12ヶ月または数年にわたる長期の計画です。ここでは、必要な資源の準備や基本方針・成長戦略の策定が行われます。
中日程計画:1〜3ヶ月の中期的な計画で、月単位で製品の種類や数量を決め、必要な資材の手配を行います。
小日程計画:1日単位の短期的な計画で、具体的な作業計画を記載し、人員の手配や作業指示が行われます。
②マスタ情報を設定する
マスタ情報の設定は、製品に関する基本的な情報を統合して記録します。
- 品目:名称、品目コードなどの情報を含む。それぞれの製品に関する識別情報を整理します。
- 構成:部品情報や製品の構成要素を記録します。製品がどのような部品から成り立っているかを明示します。
- 工程:製造プロセスの工程を列挙します。製品がどのような工程を経て作られるのかを定義します。
- 発注先:部品や資材を発注する先の情報を含めます。信頼できる供給先を確保するための情報です。
- 単価:各製品や部品の単価を記録し、コスト計算や予算策定に役立てます。
- 担当者:製品やプロジェクトに関連する担当者や責任者を指定します。
- カレンダー:稼働日やスケジュールに関する情報を含みます。作業可能な日や休業日などを記録して、生産計画を立てる際に考慮します。
これらの情報をマスタデータとして整理し、製品に関連付けて一元管理することで、データの統合性を高め、集計や分析の効率化を図ることができます。
③概要欄を記入する
マスタ情報を設定したら、概要欄を記入していきます。
④作業ごとに生産計画を立てる
その後、作業ごとに生産計画を立てていきます。担当者・開始日・終了日などを記入して「どの作業を、誰が、いつまでに完了すべきか」を明確に記入します。
⑤作業状況を変更する
作業が完了したら、作業状況を「完了」に変更します。作業状況の変更漏れがあると、管理者に余計な手間がかかってしまうので、作業完了後は、作業状況の変更を徹底するようにしましょう。
エクセルを使った生産管理は適正なのか
近年、新型コロナウイルス感染症拡大により、デジタル化の課題が目立っています。独自システムを使って管理する企業が増えている一方、依然としてエクセルで管理する企業も存在しているのが現状。誰もが一度は使用した経験があるため、作成側もつくりやすいといったメリットがあります。
しかし、エクセルにこだわるメリットはあるのでしょうか。デメリットも合わせて加味し、本当に使い続けるべきなのかを見直していきましょう。
エクセル管理のメリット
エクセル管理のメリットを解説いたします。
誰でも使える
エクセルは誰でも使えるのが大きなメリットです。今では求人票にもエクセルスキルを求める企業が一般的であり、最低限のスキルとして認知されています。
そのような時代背景からも、ほとんどの方がエクセルを使いこなせるまでになりました。管理側は一から使用方法を教える手間がなく、自分の業務に集中できるのもポイントです。
慣れていて使いやすい
エクセルで管理するメリットは管理者だけでなく、使う側のユーザーにも利点があります。例えば、社員一人一人に対する業務ストレスが少なく、普段と同じような感覚で業務に取り掛かれる点です。
新しい作業を覚えるとなれば負担が掛かるものの、作業の合間を利用して説明すれば問題ありません。人材不足が叫ばれている製造業にはおすすめと言えるでしょう。
コストを抑えられる
エクセルはコストを抑えられる面でもメリットがあります。今やMicrosoft Officeを導入していない企業はないと言っても過言ではありません。エクセル・パワーポイント・ワードなどはフル活用しているでしょう。
たとえ導入していなくても、1ユーザー約1,400円で利用可能です。別途生産管理システムを導入すれば月数十~数百万円となるケースもあり、圧倒的にコストを抑えられます。
マクロで自動化が可能
エクセルは使い方次第でマクロで自動化できるのもおすすめポイントです。マクロとは必要な作業をクリック一つで呼び出す便利な機能。例えば「ボタン一つで領収書や請求書を呼び出す」「データをもとにグラフを簡単に作成できる」などが可能です。
さらに、VBAを使いこなせれば、様々な業務が自動化できます。コストを抑えつつ業務効率を上げられるのは大きなメリットです。
他のツールと連携しやすい
データを共有したり分析したり様々なツールと組み合わせられます。どのツールも連携方法は容易であり、導入ハードルが低いのもメリットです。
エクセルの状態からそのまま一括登録できるツールもあり、担当者がIT知識に疎くても安心と言えます。
エクセル管理のデメリット
エクセル管理のデメリットを解説いたします。
同時に作業しづらい
エクセルは複数人で同時に作業しづらい点がデメリットです。誰かが開いている状態で他の方は開けないため、作業が終了するまで待ち続けなければいけません。その間に他の作業へ取り掛かってもいいですが、そのままエクセルの更新を忘れてしまう人も出てくるでしょう。
また、更新中に離席してしまうと他の人へ迷惑を掛ける場合もあります。
バージョン管理がしづらい
後述するのですがエクセルは常にバージョンアップを行っています。Microsoft Officeには過去のバージョンを管理する機能はなく、自分自身でこまめに管理する必要があるのです。
一人一人がマメに管理しなければならず、PCに疎い人は管理を行うのはむずかしいかもしれません。
データサイズによっては処理が重くなる
エクセルはデータサイズによっては処理が重くなるケースもあります。
例えば、容量の大きい画像を添付したり、そもそもPCスペックが低かったりするとスムーズに動きません。場合によっては数分で終わる作業も10分以上掛かるケースもあるのです。
作業が遅くなるだけでなく、作業者一人一人にストレスが掛かってしまうでしょう。
属人化してしまう可能性がある
マクロで自動化すると作業効率は格段にアップします。高度な技術を用いれば生産性はさらに上がるでしょう。
しかし、ハイレベルな技術を駆使するということは、一部の作業者しか開発内容を把握できないとも言えます。例えば、作成した方が退職してしまえば、何かシステム上に問題があっても対応できません。
マクロを使用する場合はそのようなデメリットも考慮しておきましょう。
互換性がない
Microsoft Officeは定期的にバージョンアップを行っています。エラーや不具合を修正している点ではメリットですが、使用感でやや不便な点も見受けられるのです。
例えば「今まで気に入っていた機能が急になくなった」「昔使っていたプログラムのほうが便利だった」など、不満の声もしばしば。バージョンアップがコンスタントに行われるからといって、必ずしも使いやすくなるわけではありません。
履歴管理がしづらい
エクセルは履歴管理がしづらい点もデメリットです。エクセルは共有ファイルをそれぞれのユーザーが管理できるため、勝手に複製したり誤って削除できたりします。
社員間で混乱が起こるケースもあるだけでなく、誰が行ったのか履歴を追いにくいのも不便な点です。原因究明に時間がかかり、結果的に作業効率を下げてしまいます。
生産計画を作成するための手順
生産計画を作成するための手順を解説いたします。
需要の予測を立てる
生産計画を作成する場合はまず需要の予測を立てていきましょう。最初のうちは過去の実績をもとに作成するのがポイントです。
「去年は100台売れたから今年も100台を目安に目標を立てよう」「過去2年は10台13台と売上があり、その数値を参考にする」など、過去の流れを読み取っていくと良いでしょう。
しかし、年によって販売数は変わるため、流行の流れやユーザー心理を予測して組み立てていくのがおすすめです。
部品調達や製造の計画を立てる
需要予測が立ったら次は部品調達や製造の計画を立てていきましょう。具体的には「どれくらい発注をするか?」「製造する量やペースはどの程度にするか?」などを決めていきます。
一般的にはリードタイムが短ければ売上アップにつながるため、段取りや行動の無駄を可能な限り省いていきましょう。
エクセルで生産計画を作成する際のポイント
エクセルにおける生産計画作成の要点を解説します。
シートを分ける
エクセルで生産計画を作成する際は細かくシートで分けていきましょう。発注数・納期・計画などに分類していくと見やすく、誰でも理解できるシートが完成します。
また、大切な情報が埋もれるケースを防げるため、管理ミスの防止につながるのです。さらにシートの見出しに色を付けていくと分かりやすくなります。
ガントチャートで可視化する
生産計画はガントチャートで見える化するのもおすすめです。ガントチャートは進捗状況が一目で分かる表になります。
横軸が期間、縦軸がタスク(工程)によって構成されており、進行具合をグラフで表示。「今の段階で誰がどこまで工程を終えているか?」「この工程を完了したのはいつか?」などをシートから追えます。効率化を図るためには欠かせないツールです。
関数を使って自動化する
関数を使って自動化しても良いです。例えば、関数を使えば合計・平均・条件判定などを毎回手動入力する必要はありません。
関数の基本的な使い方さえ押さえておけば、誰でも簡単に利用できます。むずかしい計算も自動で行ってくれるため、効率化につながります。
作業別エクセル生産計画表の使い方
作業別エクセル生産計画表の使用方法を解説します。
生産計画の基準年月を設定
エクセルで生産計画を使う際は基準年月の設定が重要です。具体的には大日程・中日程・小日程の計画を立てていきましょう。
大日程は半年から1年の長期計画、中日程は1ヵ月単位、小日程は毎日行われる作業です。各日程の基準年月を設定しておけば、よりスムーズに作業が進められます。
マスタ情報を設定
続いて行うのはマスタ情報の設定です。マスタには品目・構成・発注先などがあります。製造物を設定し、発注先の会社情報などを入力していきましょう。
マスタ情報は日々変更される可能性もあるため、その都度定期的に更新していく必要があります。
生産計画表の概要欄を記入
マスタ情報の設定が終了したら生産計画表の概要欄を埋めていきましょう。概要欄は計画の内容をあらためて説明したり、注意事項を案内したりする項目です。
例えばパソコン製造であれば「パソコンモニターは来月中までに100台完成させる」「モニターはロゴまで入れる」など。誰もがスムーズに遂行できるよう漏れなく記入していきましょう。
各作業の生産計画を作成
続いては各作業の生産計画を作成していきます。前述した大・中・小日程の計画をさらに落とし込み「誰がいつまでに完成させるか?」を決めていきましょう。
生産計画は高すぎず低すぎず、頑張ったらようやく手が届く程度で設定するのもポイントです。過去の実績や事例も参考にしながら作成していきましょう。
作業状況を「完了」に変更する
最後は状況を完了に変更します。長く作業中のままにしておくと「人員を投入しなければいけない」「早く終わらせるための計画をあらたに練らねば」など、管理者に不要な手間が掛かります。
見過ごしやすいポイントのため、全従業員で周知していきましょう。
スムーズに生産計画を管理するポイント
生産計画を管理するポイントを解説します。
コミュニケーションツールを見直す
スムーズに生産計画を管理するにはコミュニケーションツールの見直しが必要です。
例えばチャットを利用すれば業務効率は格段に上がります。既読機能やグループチャットが付いており、リアルタイムで意思疎通が図れます。
メールよりもスピード感を持って連絡が取れるため、あらためて連絡の手段を見直していきましょう。
情報共有をこまめに行う
生産計画を管理する際は情報共有をこまめに行っていきましょう。報連相をマメに行えば、たとえトラブルが起きても早い段階で対処できます。
反対にトラブルの共有が遅れてしまうと、二次災害にもつながりかねません。良い報告も悪い報告も従業員間で報告をしていきましょう。そのためにも、コミュニケーションが取りやすい空気をつくるのも大切です。
生産管理ツールを活用する
スムーズに計画を遂行するには、生産管理ツールをうまく活用するのもおすすめです。ツールを導入すればリアルタイムで在庫数や生産情報を確認できます。
例えば「エクセルの入力ミスにより、実際の在庫数とデータに差異があった」のようなミスも防げるのです。
また、計算式が既に備わっているため、煩雑なシステム構築作業も不要。エクセルで発生するデメリットを可能な限り補えるのです。
生産性の高い管理方法を選びましょう
製造業の生産計画を管理するには緻密な作業が必要です。その中でも誰もが使いやすいエクセルを利用している企業は多いでしょう。操作をあらためて説明する手間が省け、コストパフォーマンスも良いです。
とはいえ、計画項目数や従業員数が多くなれば、エクセルでの管理も限界がきてしまいます。「もっと効率良く管理したい」「エクセルのアナログ感を極力なくしたい」などの悩みがある方は生産管理ツールを活用してみましょう。