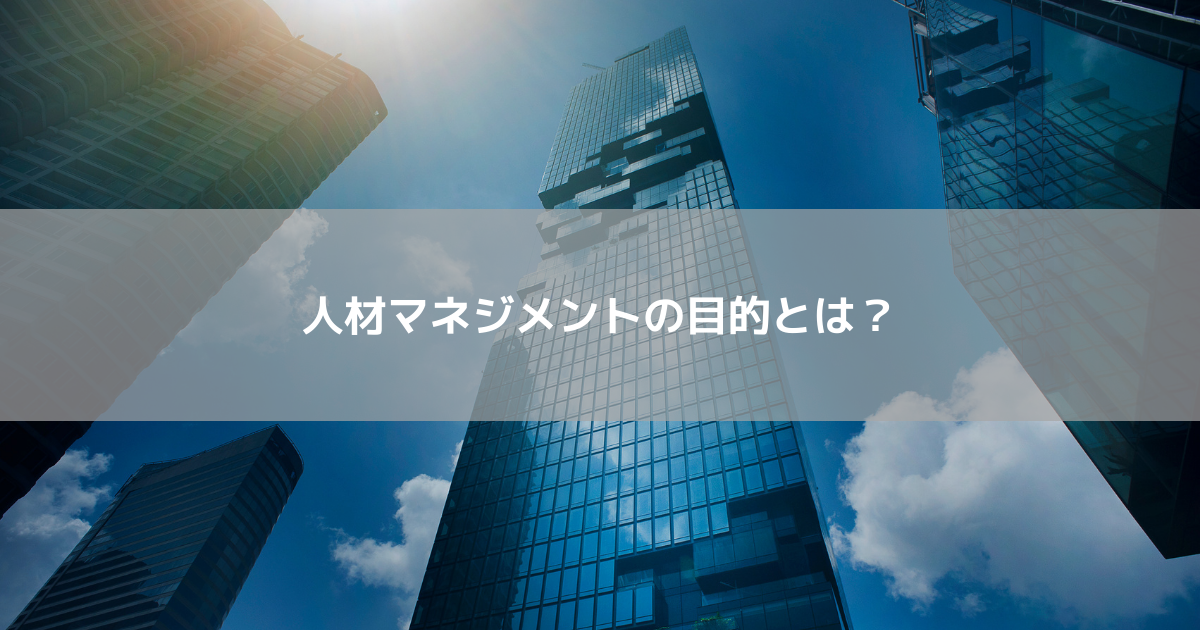人材育成におけるコーチングの利点と具体的なやり方とは?
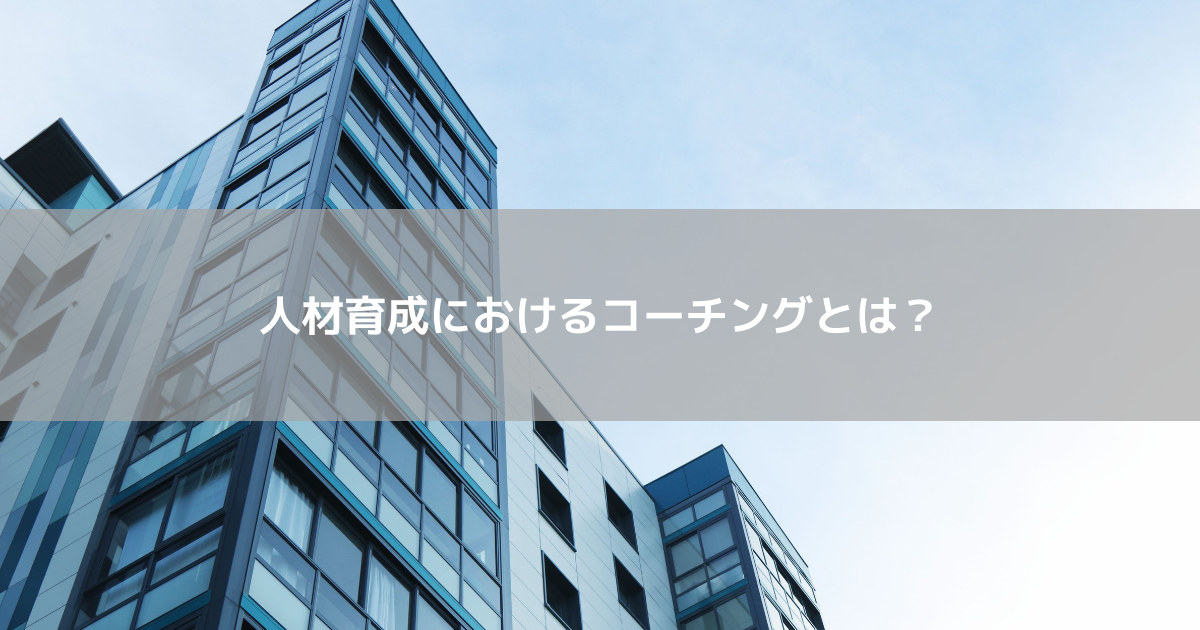
人材を育成するにあたって、ただ単に仕事を教えていれば、部下が自ずとスキルを身に付けることができるとは限りません。時と場合に応じて、最初から答えを教えてあげたほうがいいケースも存在しますし、その一方で部下自身が頭を使って考えることで効果的になるケースも存在します。それぞれを「ティーチング」と「コーチング」と呼ぶのですが、本記事では特に「コーチング」のメリットについてご紹介しましょう。
コーチングとは
一般的に用いられるコーチングとは、個人や組織の目標達成をサポートすることを指します。使われる場面としては、教育やスポーツ、ビジネスなど、非常に幅広い分野が考えられます。
正確な定義としては「コーチングとは、目標達成に必要な要件を相手とともに確認した上で、相手の自発的な行動を促す手法」とされます。
そのため、指導者が何かを教える行為だと思われがちですが、基本的な姿勢は「両者が同じ目線に立ち、目標達成のために共に成し遂げる」というものです。
上記より、企業内でのコーチングを定義するとすれば、「上司や専門家と部下が対等な目線で共同して組織の全体目標を個人の価値観とすり合わせながら、個人のジョブや目標を設定・実行していくこと」と言えます。
ビジネスシーンにおけるコーチング
ビジネスシーンでコーチングを活用できる場面として、社員教育やマネジメントが挙げられます。それぞれを詳しく紹介します。
社員教育
社員教育の場で、従業員の思考能力や問題解決スキルを養うための手段として、コーチングは有効です。組織を持続的に成長させていくためには、自発的に考え、問題を自ら解決できる人材の育成が鍵となります。
ビジネスシーンにおいて、問題解決スキルが活かされる場面は多いため、組織がコーチングを取り入れる重要性が高まっているのです。
マネジメント
コーチングを活用したマネジメントの目的は、従業員が目標達成のための能力や考え方を養うことです。問題に直面したときに、個人が自ら考え、行動できる人材育成のために、コーチングを活用したマネジメントが効果を発揮します。
変化が激しくなりつつある現代では、柔軟な考えや新しいアイデアを構築できる人材が求められるようになっています。自発的に変化に対応できる人材を確保するためにも、コーチングによるマネジメントは、組織の発展・成長に大切な取り組みとなります。
コーチングの種類
コーチングには主に社内人材に実施させるパターンと外部の専門企業に委託するパターンの2種類が存在します。
社内人材がコーチングを実施する場合は、費用の抑制や、組織内のコミュニケーションが活発化などのメリットがある一方で、上司の力量次第では組織の風通しが悪くなるなどのリスクも伴います。
外部の専門企業に委託する場合は、安定的に高いクオリティのコーチングが供給されることが期待される一方で、費用が嵩むといったデメリットがあります。
パーソナルコーチング
パーソナルコーチングは、一般社員や従事者を対象とするコーチングです。
パーソナルコーチングは、問題解決や戦略立案に関する能力を鍛える目的や、メンタル面にフォーカスした形式などがあります。複数の指導者によるセミナースタイルや、コーチと1on1での会話で進行され、受講者のスキルや目的を踏まえて実施されます。
パーソナルコーチングは、一般的に複数回・数ヶ月をかけて、課題解決や目的達成に向けて継続的に従業員をフォローしていきます。パーソナルコーチングでは、クライアントが自身の潜在能力を最大限に発揮し、個人的な目標を達成するのに役立ちます。
エグゼクティブコーチング
エグゼクティブコーチングは、経営者やマネージャーなどの組織を統率する立場の方を対象とするコーチングです。実施形態はパーソナルコーチングと同様ですが、ターゲットがマネージャー層であるのが特徴です。
エグゼクティブコーチングでは、組織の変革に関わる意思決定スキルの向上や、企業の幹部候補者育成などを目的としています。
変化が激しく、将来の予測が難しい現代において、経営者には自社の現状や、情勢の変化を踏まえ、経営判断を瞬時に行わなければいけません。企業を発展させるために、組織の核となる経営者の責任は重大となります。
経営者の意思決定力・判断力のスキルアップを促すエグゼクティブコーチングは、現代において需要が高まっているのです。
コーチングとよく似た言葉とその違い
コーチングと似た言葉として、以下があります。
- コンサルティング
- ティーチング
- メンタリング
それぞれの特徴やコーチングとの違いなどを詳しく紹介します。コーチングと混在しないように、意味や概念を押さえておきましょう。
コンサルティング
専門的な知識や経験を提供し、問題の解消に向けて具体的なアドバイスや戦略を提供するのがコンサルティングです。専門知識を持つコンサルタントが、クライアントに対して解決策を提案する役割を果たします。
質問を通じてクライアントを誘導し、自分で答えを見つける力をつけるための手助けをするコーチングに比べて、コンサルティングは答えやアドバイスを提供する点で違いがあります。
ティーチング
コーチングとティーチングの違いは、学習プロセスと役割にあります。コーチングは主に自己発見と問題解決に焦点を当て、クライアントが目標を達成するために自身の能力を引き出す手助けをします。
一方、ティーチングは知識の学習に焦点を向け、教師側は学生に特定分野に関する情報やスキルを教えます。教師は通常、カリキュラムや教材に基づいて教育内容を提供し、生徒に情報を伝える役割を果たします。
コーチングは自己発見と問題解決スキルの向上を促進し、クライアントの実務に関する技術や、洞察力の発育を促すのに対して、ティーチングは知識とスキルを伝えることに焦点を当てる違いがあります。
メンタリング
メンタリングは経験豊かなメンターが、知識や経験を共有し、指導するプロセスです。コーチングは実務に関する技術や知識の支援が多いですが、メンタリングではメンタル面での精神的サポートが中心とされます。
コーチングよりもメンタリングの方が期間が長くなる傾向があり、仕事に関するスキルや技術だけではなく、精神的な悩みや課題にも対話を重ねながら向き合います。実務経験者が対象となるコーチングと異なり、メンタリングでは新社会人など、社会経験のない方が対象となることもあります。
コーチングのメリット
コーチングを行う利点としてはいくつか考えられますが、特に以下の4つを紹介します。
主体性を高める
最もわかりやすいメリットとして、「主体性が高まる」という点があります。ただ闇雲に知識やノウハウを詰め込まれただけの社員は、自身の頭で考える機会を失います。その結果として、与えられた業務だけをこなすようになり、アイデアなども出にくくなるでしょう。新しいアイデアを出せる社員を育成できないということは、会社としての成長も止まってしまう原因になるため、「コーチング」は必須とも言えるでしょう。
潜在能力を引き出す
コーチングを行うことによって、社員自身の頭で考える癖がつき、これまで気づかなかった潜在的な能力を引き出すことにつながることがあります。何か新しい目標に向けてプロジェクトを進める際など、既存のアイデアだけでは発展しないような場合に役立つでしょう。ここで重要なことはコーチングにおいて、社員の思考を広げられるようなコミュニケーションを意識することです。
学習意欲の向上
主体的に行動できるようになる点がコーチングの強みと言いましたが、その影響によって社員自ら新たに学ぶ姿勢が見られる可能性が高まります。つまり学習への意欲が高まるのです。一度モチベーションが向上してしまえば別の場面でも大いに役立つため、この効果を利用しない手はありません。
メンバーとの信頼関係が向上する
コーチングは、上司とメンバーの信頼関係向上にもつながります。上司や先輩社員が、部下と対等な関係で向き合うことで、交流する機会が増加するため、お互いの考えや価値観を共有しやすくなるのです。
会話をする機会が少なかった社員同士の関係が深まることで、円滑なコミュニケーションがしやすくなり、業務効率の促進にもつなげられるのもコーチングのメリットと言えます。
立場が違う社員同士で、話し合う機会を広げられるのがコーチングの利点です。
コーチングのデメリット
利点だけに注目するとコーチングをしない理由が見つからないと思います。ですがその反面、障壁となる要素も含まれるのです。こちらも大きく分けて3つ解説します。
時間が必要
コーチングの効果は即座に現れるようなものではありません。数回のコミュニケーションを取ったからといって、主体的に行動できる社員が増えるといった都合の良いものではないのです。確実な効果を期待するためには、対話などのプロセスを繰り返し、じっくりと時間をかけなければなりません。ですが人材の育成には時間がかかるものだということをあらかじめ把握しておけば、デメリットとは感じないでしょう。
効率的な育成が困難
集団研修のような「大人数を相手に一度で開催できる効率性」とは真逆で、コーチングは個人単位での育成になるため効率的とは言えません。また社員が自分自身で答えに辿り着くまで導いたり、その答えを辛抱強く待つ必要があるため、人によって期間に差が出てきてしまいます。そういった理由で、効率的な育成は難しいと言えるでしょう。
コーチのスキルが必要
コーチングには時間がかかり、非効率的な育成になるため、コーチ側にもじっと我慢して待てるようなスキルが求められます。社員自ら答えに辿り着けるように、円滑なコミュニケーションを図ったり、会話の中で社員の選択肢の幅を広げられるようなテクニックも重要な意味を持つでしょう。
コーチングやり方
最後に具体的なコーチングのやり方について解説します。まずは以下の5点に注意しながら、社員とコミュニケーションを図れるように意識しましょう。
相手を肯定、認める
コーチングにおいて重要なことは、社員が話しやすいような雰囲気を作り、自身の考えを隠さず伝えてくれるように努めることです。まずは相手の話を聞き入れ、行っていることが間違っていると感じても、真っ向から否定せず、まずは肯定するところから始めましょう。あくまで円滑なコミュニケーションを取ることが目的であることを覚えておくと良いでしょう。
親身に傾聴し、相手を理解する
相手を肯定しながら話を聞いていても、ただ相槌を打つだけでは十分ではありません。しっかりと相手の話に関心を持った上で接し、「この人になら話しても良いかな」と思ってもらえるようにしましょう。その上で相手の立場に寄り添って、今後どうなっていきたいのかを深掘りしていくと上手くいきやすいです。
質問による情報の整理
コーチングは事情聴取ではありません。一方的に「なぜ」や「何が」などと詰問していては、相手も居心地が悪くなってしまいかねません。相手が話した内容を自身の頭で整理できるように、効果的な質問を繰り返すことで、具体的にどうなりたいのかを引き出す工夫が必要になります。
フィードバックによる気づき
ひと通り社員から話を聞き出すことができれば、コーチから見た客観的な視点による考えを織り交ぜた上で、フィードバックしてあげると良いでしょう。そうすることで一人では絶対に気づかなかったようなことにも着目できるようになり、具体的にどのように行動していけば良いのかの指針も決まるかもしれません。あくまでコーチ視点での意見を話すようにし、考えの押し付けをしてはいけません。
具体的な行動を促す
フィードバックまで済んだら、今後どのように考えて行動していけば良いのかの提案をしてあげると良いでしょう。上でも述べた通り、考えの押し付けをするのではなく、「してみてはどうか」というスタンスでいることが重要です。そうすれば相手の考えも尊重することができ、主体的に行動できる後押しになることでしょう。
継続的に行って進捗を把握する
コーチングの実施には、継続的に社員の状況を確認し、フォローすることも大切です。目的や課題を設定した後部下を放置状態にしては、正しいコーチングとは言えません。
設定した目標に向かって、方向性は間違っていないか、進捗具合は順調そうか、などを確認する機会を作り、定期的に社員とコミュニケーションをとりましょう。
メンバーのスキルを正確に把握してコーチングに活かそう
コーチングを成功させるには、メンバーのスキルを正確に把握し、成長具合や進捗を追える環境作りが大切です。
当社が提供するスキルナビでは、メンバーのスキルや目標設定を管理する機能が充実しており、導入時もサポートチームが初期設定やデータ移行を行うため、最小限の負担で利用できます。
社員のスキル管理や評価にかかる負担を大きく削減できるため、業務効率化や管理体制の向上を目指す企業は、ぜひスキルナビの導入を検討してみてください。
コーチングを取り入れてみましょう
コーチングの効果を実感するまでには膨大な時間がかかることでしょう。またコーチ側の負担も少なくなく、相応のテクニックも必要になります。そうしたデメリットもある一方で、主体性のある社員を育てることができるため、組織全体として受けられる恩恵も大きくなります。将来的な企業の成長のために、コーチングを取り入れてみてはいかがでしょうか。