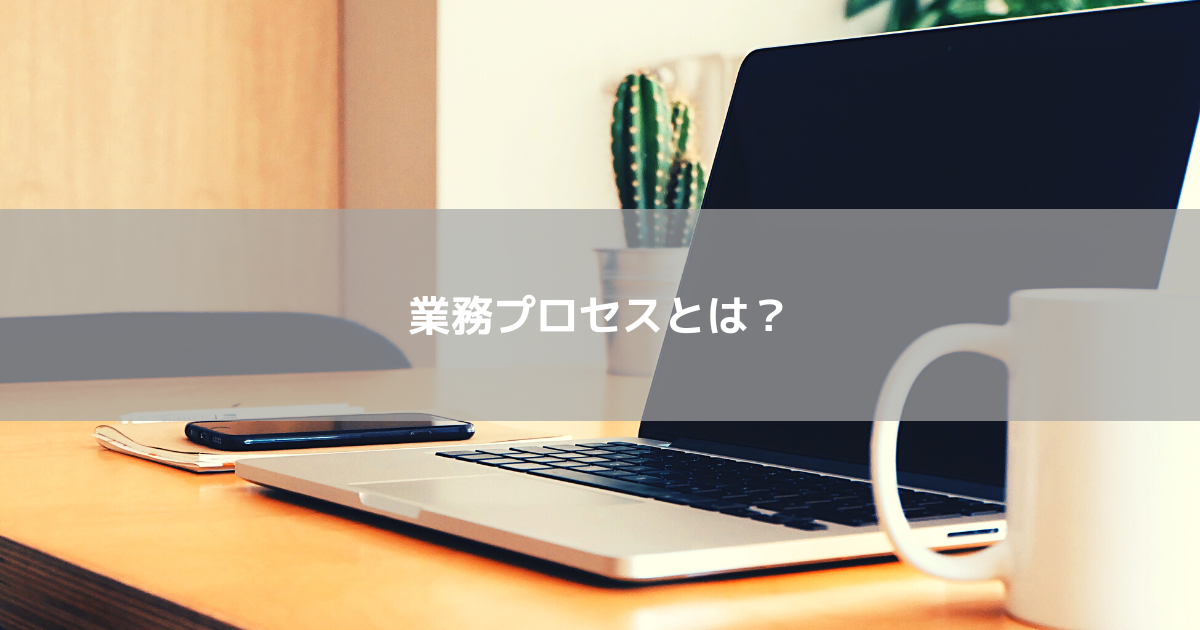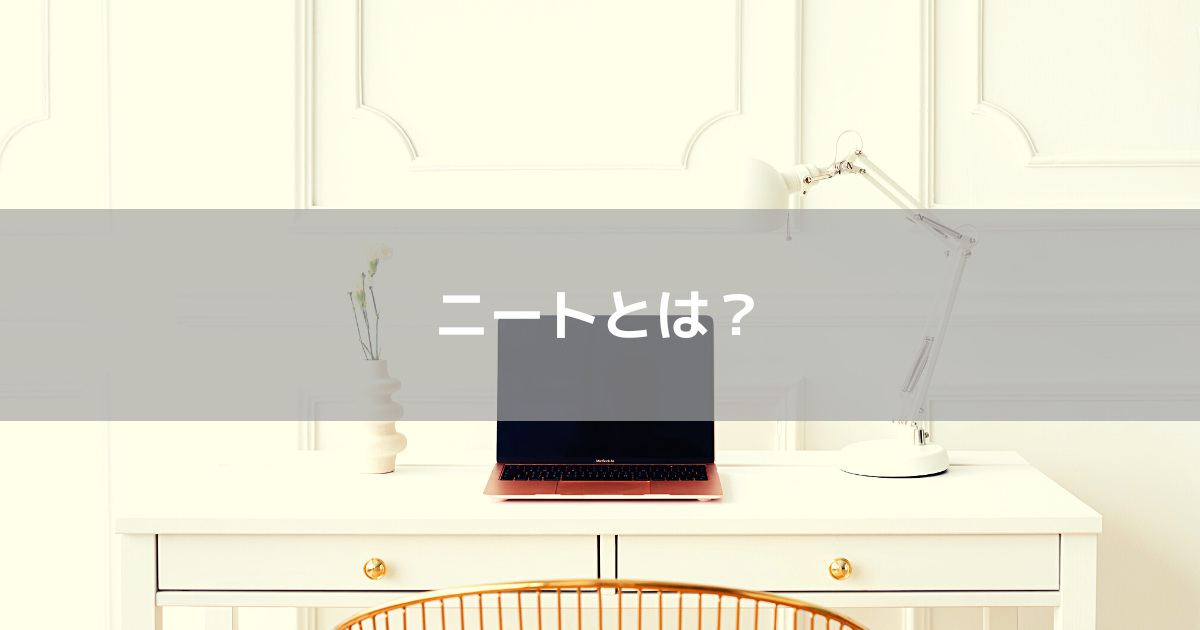人事異動の決め方は?適材適所の実現をするためのポイント
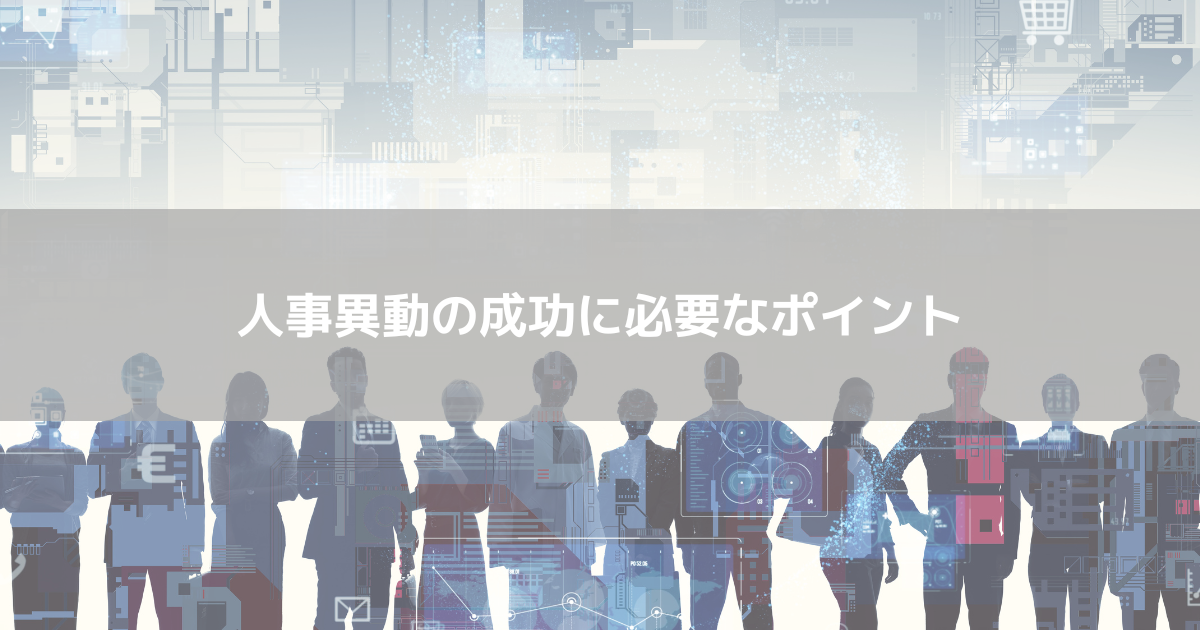
人事異動とは、企業が人事権を行使し、従業員の職位や勤務地、勤務条件などを変更する辞令を指します。
企業が人事異動を行うメリットは数多く、優秀な人材を適材適所で扱えば、企業の生産性向上にもつながります。
今回は、人事異動を成功させるための重要なポイントや、人事労務担当者が行うべき事務手続き、実施のメリットなどを解説します。
人事異動はなぜ必要?その目的とは
社員の人事異動は、企業になぜ必要となるのでしょうか。
以下で、企業が人事異動に取り組むべき意義を解説します。
適切な人材配置のため
初めに、適切な人材配置を行うためです。
人材の適材適所を実現するために、人事異動は簡便でスピーディな方法です。
社員が入職した当初は、過去の経歴やスキル、面接での印象からしか適性を判断できないため、最初から従業員のスキルや経験が活かせる適材適所を実現することは難しいといえます。
また、企業によっては「まず営業職」「まずは現場仕事」というように、企業文化を知るために最初の配属が決まっているケースがあります。
入職後の従業員の働きぶりから適性の見極めをしたり、本人にキャリアについてヒアリングをしたりして、従業員が個性を発揮できる場所を探しましょう。
人材育成のため
二つ目は、人材育成のためです。
1つの部署で長年経験を積むと、その道のプロとして成長できます。しかしその状態は、「それしかできない」と評価されかねません。
昨今はプロフェッショナル人材に注目されてはいるものの、オールマイティーに活躍できるゼネラリストの需要も引き続き高い状況にあるため、企業にはさまざまな経験とスキルを持った人材が必要です。
人事異動を行うと、従業員は新しい環境と業務内容を経験できます。
その結果、それまで企業が認知していなかった従業員の適性や性質を見つけることができ、スキルアップだけでなく能力開発にもつなげることができます。
事業戦略のため
続いては、自社の事業戦略のために必要だからです。
企業の存続と成長のためには、現状の事業だけにとどまらず、新しい事業やサービスを立ち上げたりすることが有効的です。
新規事業の立ち上げやプロジェクトの立案を行う際は、その事業の立ち上げメンバーを選定せねばなりません。
スタートする事業内容や期間を考慮し、事業を軌道に乗せられる人材を選び、人事異動を実施しましょう。
新規事業の準備だけでなく、業績による事業撤退時などにも人事異動を行います。
さまざまな事業戦略の実現を目指す際は、人事異動が必ず必要になるといえます。
組織の活性化を促進するため
次に、組織の活性化を促進することです。
企業が定期的な人事異動を実施すると、従業員の配置が入れ替わることによって、組織にこれまでになかった新しいアイデアや視点を生み出すことが可能となります。
これまでなかった価値観を組織に取り入れることで、組織の活性化を促すことができます。
生産性向上の貢献をするため
企業の生産性向上への貢献をすることも、適材適所の人材配置の目的の1つ一つです。
人事異動を行うことによって、従業員の能力を最大限に発揮し、生産性の向上を図ることができます。
コンプライアンス強化を目指すため
最後は、コンプライアンスの強化を目指すために人事異動を実施するということです。
人事異動を行うと、同じ組織、同じ部署に継続的に常駐することが少なくなるため、長期的な業務継続によるリスクを避けることができます。
これによって、不正防止や癒着防止が可能となります。
人事異動の決め方とは
会社の人事権を行使し、従業員の配置を決める人事異動ですが、どのような決め方があるのでしょうか。下記で3種類を紹介します。
人事主導型
1つ目は、人事主導で人事異動を実施する手法です。
これは「中央集積型」とも呼ばれるパターンであり、特徴は、人事部が全体の管理を行って異動先の選定なども担うことです。
企業の事業展開や経営理念などを実現するには、判断に一貫性を持たせる必要があるでしょう。
そういった意味で、人事部が配置決めを行うのは理にかなっているといえます。
ただし、現場の生の声が反映されにくくて従業員満足度が低下するリスクが高いのが懸念点です。
大企業で実施されやすいパターンですが、従業員一人ひとりの希望や能力、適性の見極めが欠かせません。
現場主導型
二つ目は、現場主導で人事異動を実施していくことです。
人事異動の影響を大きく受けるのは、実際に現場に立つ従業員である場合が多いでしょう。
本社や人事部からは判別できない悩みや不足している人材は、人事部よりも店舗や工場、支店などの現場の方が明確に認識しています。
そのため、実際に現場で働く人の声をヒアリングしたうえ上で人員配置を決めるのが現場主導型です。
現場の声が反映されやすいのがメリットですが、企業の経営理念と大きくズレないように人事部による介入も必要です。
玉突き異動型
最後は、玉突き異動型と呼ばれる手法をご紹介します。
「玉突き人事」とも呼ばれ、穴が空いたポジションを埋めるように人員を補充する異動パターンです。
官公庁や銀行が多く実施しており、一般的な企業ではあまり見られません。
穴が空いたポジションを埋める性質から、現場の声を反映するケースより人事が主導するケースが多いでしょう。
計画的であれば長期的な事業展開を見据えた人材育成に取り組めます。
ただ、従業員の不祥事などを理由にした突発的な玉突き異動型はネガティブな印象が強く、従業員のモチベーションが下がりやすいので注意が必要です。
人事異動は拒否できないの?
上項でも述べたとおり、人事異動は人事権を用いて従業員の職位や勤務地、勤務条件などを変更する辞令のことをいいます。
基本的に、企業が人事異動を実行する際には、各従業員の希望を反映する義務はありません。
人事異動の進め方である現場主導型では、従業員の希望を反映しやすく、逆に中央集権型の決め方では、一般的に従業員本人の希望は提出できないことが多いです。
従業員の志向や今後のキャリアを左右するミスマッチな人事異動を行ってしまうと、従業員のエンゲージメントが低下する要因にもなり、最悪の場合離職が発生してしまう可能性があり得ます。
そのため、企業が保有する資本の一種である従業員を有効的に活用するためにも、従業員の意向とすり合わせた配置を行うことが望ましいでしょう。
人事異動制度
近頃、自己申告制度や社内公募、フリーエージェント(FA)制などを活用し、従業員の希望を反映する人事異動制度を取り入れる企業が増加傾向にあります。
- 自己申告制度は、従業員が自身のキャリア意向を基に希望を出せる仕組み
- 社内公募:人材を募集する部署が求人を社内へ展開し、希望する従業員が応募できる仕組み
- フリーエージェント制:異動を希望する社内従業員をスカウトする
従業員の希望を完全に聞き入れる必要はないものの、従業員エンゲージメント低下や離職防止の一貫として、このような制度を取り入れて配慮を行うことが重要です。
人事異動で適材適所を実現するための5つのポイント
では、どのようにして人事異動で従業員の最適な配置を実現していけばよいのでしょうか?
ポイントを下記でピックアップしてお伝えします。
1.従業員のスキル・適性を正確に把握する
1つ目は、従業員のスキルや適正を性格に企業が把握するということです。
各従業員の能力や経験を一覧化し、どこの誰がどのような強みや弱みを保有しているのかを明確にしておくことが重要です。
異動を考課する際には、異動検討先の部署や、その業務と従業員の性格的な向き不向きの確認も必要です。
評価をする際は、偏りが発生しないよう客観的な判断を加味する必要があります。
2.本人の意向を尊重する
続いては、本人の意向を尊重するということです。
従業員本人のキャリアや意向を踏まえ、今後異動の意思があるのかや、今後のキャリアプランをどう考えているのかなどを事前に認知しておくことが重要です。
企業が従業員の意向を認識するために、個別上長とのミーティングなどでヒアリングの場を設けて話し合うことで、従業員のモチベーションを常に把握することに寄与します。
3.部署間のバランスを考慮する
部署間の従業員の負担などのバランスも考慮することも人事異動においては重要です。
部署内の人員バランスを考慮することで、業務負担や偏りが発生しないように取り組むことができます。
また、チームの相性を考慮し、コミュニケーションの円滑化を図ることも可能となります。
4.透明性のある異動プロセスを設計する
人事異動に透明性を持たせることも重要です。
従業員本人に評価基準を明確に伝えることで、従業員本人も異動をする際納得感を持って対応することが可能です。
また、その際、併せて異動理由もきちんと伝えることで、異動先でも本来の力を発揮してもらうことが期待できます。
5.ジョブローテーションを導入する
最後のポイントは、ジョブローテーション制度を取り入れるということです。
ジョブローテーションは一定期間ごとに従業員を異動させ、幅広い業務や部署を経験してもらう人事制度のことを指します。
実施することにより、従業員はさまざまな業務経験を積むことができ、適性や苦手分野を見極めることが可能となります。
ジョブローテーション制度は従業員一人ひとりのキャリアの幅を広げるきっかけにもなり、適材適所の人事異動に役立ちます。
適材適所を人事異動で実現できた際の効果
上項までで、人事異動の目的やポイント、種類を解説してきました。
このような点に留意しつつ、人事異動によって従業員の最適な配置を実現できた場合、企業にはどのような効果がもたらされるのでしょうか。
下記にて説明します。
離職率の低下と従業員の定着促進
適切な人事異動を企業が行うことによって従業員のエンゲージメントを向上させることができ、従業員一人一人の企業への帰属意識を高めることが可能です。
自分のスキルや得意領域、今後のキャリア志向に沿った業務を実行することができれば、従業員も働くモチベーションや成長実感を得られるので、離職率の抑制につながります。
生産性の向上と業務効率化
従業員の得意分野を活かした配置を行うことができれば、個々のパフォーマンスが最大化され、結果的に従業員の生産性向上につながります。
最適配置を叶えれば叶えるほど、企業の生産性向上にもつなげることができます。
また、これまで複数人で実行していた業務を、その業務が得意な従業員に実行してもらうことで工数削減にもつながり、業務の効率化も図れます。
コスト削減効果
人事異動によって各従業員の定着率が高まることで、採用コストの削減にもつながります。
離職が多ければ多いほど、採用を実施し人数を補填せねばならず、例えばエージェントを活用している企業は採用コストが嵩んでしまいます。
人事異動で適切な従業員を最適な部署や業務に配置することによって、結果的に企業全体の無駄なコストの削減に寄与するのです。
人事異動におけるよくある失敗
従業員を適切な部署や業務に配置したとしても、企業としてメリットを享受できない場合が考えられます。
本項では、人事異動を実施したとしても、失敗してしまう可能性があるポイントを記載します。
納得感の欠如
従業員が納得しないまま、企業方針だけで強引に従業員を異動を決定してしまうと、従業員の不満やモチベーション低下を招いてしまいます。
従業員が納得しないまま異動を実施してしまえば、従業員の働くモチベーションの低下や、離職にもつながってしまうため、企業側は十分な説明と理解を求めることが重要となります。
人事異動制度の不完全運用
社内公募制度などの、従業員の希望を反映する制度を取り入れてもうまく応募人数が集まらなかったり、配置後に従業員の成果創出が機能しない場合は、現場との調整が必要です。
現場で具体的にどのような業務が発生するのかという点や、どのような人物が要件に沿うのかなど、社内でも調整が必要です。
社外の求人募集と同じく、社内の制度としても多くの従業員が利用できる体制を整えることが企業には必要となってきます。
人事異動で失敗しないために…!
人事異動制度を失敗させないためには、下記のような取り組みが必要でしょう。
社員の情報把握
企業が優秀な人材の流出を防ぐためには、従業員個人の希望や適性に合った人員配置の実現が重要であり、そのために欠かせないのが従業員の情報をあらかじめ把握しておくことでしょう。
管理すべき項目で必要な情報の例は、下記が挙げられます。
- 入社時のキャリア志向
- 過去の経験
- 保有スキル
- 所有資格
- 異動を希望するか
- 異動先(エリア、支店、業務内容など)の希望
- 過去の人事評価結果
本人の希望をヒアリングする際は、従業員が自由に発言できる雰囲気づくりに尽力したり、管理職のコーチング能力を高めておくことも有益です。
さまざまな情報を日頃から収集しておき、スキル管理システムやタレントマネジメントシステムなどで管理しておきましょう。
人事異動ルールの明確化
企業が人員配置を行い、従業員の納得感を高めるためには、企業が一貫した対応をする他、はっきりとルールを定めておくべきです。
例えば、就業規則に人事異動が拒否できない旨を記載する、入社時にルール説明を行う、人事評価制度を詳しく伝えておくといった対応を徹底しましょう。
一般的に企業に雇用される従業員は、企業の指示に従う必要があります。
異動命令も同じく拒否できるものではありませんが、頭ごなしに「拒否は許されない」と伝えるのは従業員のエンゲージメントを下げる要因になります。
人事異動のルールは必要ですが、従業員の気持ちを無視しないような仕組みづくりや配慮を忘れないようにしましょう。
本人に理由を提示
人事異動で失敗しないために重要なのが、従業員本人へ異動理由を伝えることです。
人事部としては将来のキャリアを鑑みての異動だとしても、従業員からすると「能力不足だったから」「期待に応えられなかった」とネガティブな印象を受けるケースがあります。
これでは、従業員自身が異動後の仕事に納得できず、離職を選びかねません。
人員配置が納得できる結果となるように、異動理由をはっきりと伝えておきましょう。
適正に人事異動を行いましょう
人事異動は各企業では頻繁に行われている手法です。
しかしながら、成功させるためにはさまざまなポイントを押さえなければなりません。
適切な人員配置を実現するためには、企業の事業展開や将来像だけでなく、従業員個人の希望や適性も考慮する必要があります。
適切な人事異動は、企業にも従業員にも多くのメリットをもたらすため、メリットを最大限に享受するためにも、実施の際は目的意識を持って取り組みましょう。
人事異動の際、従業員が保有しているスキルや資格、適性などを管理したデータベースを参照すると工数削減にもつながります。
当社が提供するスキルナビでは、従業員のスキルや適性の見える化、管理を実施できるほか、そのデータを用いて育成施策に落とし込むことが可能です。
適切な人事異動を行いたい方は、ぜひ当社にお問い合わせください。